大学の学費が払えない場合の対処法|奨学金や公的支援制度を解説

この記事の監修者
荒井 美亜
貸金業務取扱主任者、2級FP技能士、税理士科目合格者、日商簿記1級、全経簿記能力検定上級
みんなのモビット担当
立教大学経済学部卒、立教大学大学院経済学研究科修了(会計学修士)。出版社、Webマーケティングの会社に従事する中で様々な金融関連の資格を取得。クレジットカードやファクタリングの知識も持ち合わせ、お客様からマネー相談を受けた経験も多数。
この記事でわかること
- 大学の学費を払えない場合は「除籍処分」または「自主退学」となる可能性がある
- 学費が払えない場合は奨学金や公的支援制度の利用を検討してみる
- 一時的に学費を支払えない場合はカードローンの利用も有効
大学の学費の支払いができなかった場合、除籍処分や自主退学となる可能性があります。そのような事態を回避するためには、奨学金や公的支援制度をうまく活用することが必要です。
今回は、大学の学費が払えないとどのような事態に陥るのか、また、納付が困難なときの対処法について解説します。
コラムの目次
大学の学費が払えないときに起きること

大学の学費は国公立大学でも平均で年間50万円以上かかるため、在籍する4〜6年の間には学費の支払いが難しいタイミングもあるかもしれません。しかし、学費が払えなければ、「除籍処分」もしくは「自主退学」となる可能性があります。
ここでは、学費が払えない場合に起きることとその影響について解説します。起こり得る事態を事前に把握し、予防策を考えておきましょう。
除籍処分となる可能性がある
学費を長期間滞納した場合は、除籍処分となる可能性があります。除籍処分とは大学側が学生の籍を抜く手続きで、事務的な処理によって在籍者名簿から削除されてしまいます。
除籍処分となった場合、履歴書に「大学中退」と記載しても問題はありません。しかし、実際は自主退学とは異なるため、成績証明書が発行されなかったり、退学証明書ではなく除籍証明書が発行されたりするなど、その後の進路に影響が出る可能性があります。
ただし、学費未納となってもすぐに除籍処分になるわけではありません。大学から学費の振込用紙が再発送されても対応しなかったり、何カ月も連絡がつかなかったりした際にやむなく除籍処分となります。
除籍処分となるタイミングは大学によって異なるので、学則等であらかじめ確認しておきましょう。
自主退学となる場合がある
除籍処分とならない場合でも、自主退学を迫られる可能性があります。
長期間の学費未納が発生した際、大学側は「このままだと除籍処分となり得ます」といった通知をする場合があります。この時点で学費を支払える見込みがなく、除籍処分を免れたいのであれば、自主退学を選択する必要がでてきます。
大学で必要になる学費
大学の学費は国公立と私立で金額が大きく異なりますが、まとまった資金が必要になることには変わりがありません。また、私立は文系・理系でも学費に差があるため、事前に確認して資金計画を立てておく必要があります。
授業料だけでなく入学金が必要であり、私立大学の場合は施設設備費等もかかるため、必要な金額が多くなります。
国立大学・私立大学の入学金や授業料の一例は以下の通りです。
| 大学 | 入学金 | 授業料(年間) |
|---|---|---|
| 国立大学 | 282,000円 | 535,800円 |
| 公立大学 | 391,305円 | 536,363円 |
| 学部 | 入学金 | 授業料(年間) | 施設設備費 |
|---|---|---|---|
| 私立大学 文系 | 223,867円 | 827,135円 | 143,838円 |
| 私立大学 理系 | 234,756円 | 1,162,738円 | 132,956円 |
| 私立大学 医歯系 | 1,077,425円 | 2,863,713円 | 880,566円 |
| 私立大学 その他学部 | 251,164円 | 977,635円 | 231,743円 |
参照元:文部科学省「令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額(定員1人当たり)の調査結果について」
学費が払えない事態を回避するため、必要な金額を早い段階から把握しておきましょう。
大学の学費が払えないときに検討するべき対処法
大学の学費が払えない場合、何の対応もしなければいずれ除籍処分となってしまいます。学歴は就職活動等に影響を与える可能性もあるため、除籍処分はできる限り避けたいところです。
ここでは、大学の学費が払えないときに検討するべき対処法について解説します。事前に確認し、必要な際にすぐに対応できるようにしましょう。

大学に支払い方法の相談をする
大学に学費の支払いについて相談をすることで、大学独自の支援制度の案内や、延納・分納・減額の対応をしてもらえる可能性があります。利用可能な制度は大学によって異なるため、まずは大学の担当者に相談してください。
| 延納 | 学費の支払い期限を延長する |
| 分納 | 学費を分割して支払う |
| 減額 | 学費の金額そのものを減らす |
延納が認められれば支払い期日を延長してもらえるので、その日までに支払いが完了すれば問題はありません。分納が認められた場合は、学費を分割で支払うことができます。
また、大学の判断で学費の減額が認められるケースもあります。減額制度の有無は大学によって変わってきますが、学費の負担を軽減できる可能性があるため、まずは大学に相談をしてみましょう。
奨学金を利用する
奨学金を利用することで学費が確保できる可能性もあります。基本的に在籍中でも申込可能なので、大学の奨学金窓口に相談してみましょう。
| 奨学金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 独立行政法人 日本学生支援機構 (JASSO)の奨学金 | 文部科学省が所管する奨学金制度で、将来返還が必要な「貸与型(無利子・有利子)」と返還の必要がない「給付型」がある |
| 大学独自の奨学金制度 | 大学が独自に提供するもので、制度ごとにさまざまな条件が定められている |
また、大学で案内される奨学金以外にも、自治体や民間企業・団体が運営する奨学金制度も選択肢になります。
| 主な奨学金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 自治体の奨学金制度 | 自治体が提供するもので、制度ごとにさまざまな条件が定められている |
| 新聞奨学金制度 (日本経済新聞育英奨学会、毎日育英会など) | 在学中新聞配達業務をおこなうことで、学費・生活費の一部もしくは全部を新聞社が給付する |
| 病院奨学金 (独立行政法人 国立病院機構、徳洲会グループなど) | 卒業後に指定された病院・施設で規定の期間働けば、貸与された奨学金の返還を免除する |
| 民間企業の奨学金 (公益財団法人 コカ・コーラ教育・環境財団、DAISO財団など) | 民間企業が独自に提供するもので、制度ごとにさまざまな条件が定められている |
| 一般財団法人 あしなが育英会の奨学金 | 病気・災害・自死で保護者を亡くした、または親が1級から5級の障害認定を受けている学生に貸与する |
| 公益財団法人 交通遺児育英会の奨学金 | 保護者が交通事故で死亡、または後遺障害のため働けなくなった学生に貸与する |
自治体によっては奨学金の返還を支援する制度がある場合もあるので、将来返還に困った際の選択肢として、奨学金を利用する時点から確認しておいても良いでしょう。
ただ、返済が必要な奨学金については、借りる金額が増えるほど月々の返済額が増えたり、返済期間が長期化したりするリスクが出てくるので、慎重に検討してください。
教育ローンを利用する
教育ローンには、「国の教育ローン」と呼ばれる日本政策金融公庫の教育一般貸付と、銀行などの金融機関で利用できる教育ローンがあります。
| 教育ローンの種類 | 内容 |
|---|---|
| 国の教育ローン (日本政策金融公庫の教育一般貸付) | 日本学生支援機構等の奨学金と併用でき、上限350万円まで年2.40%(2024年5月時点)で借入できる |
| 金融機関の教育ローン | 借入金額や金利は審査により決定される |
どちらも学費の工面に有効ですが、特に国の教育ローンは融資までに時間がかかるため、必要時期の2〜3カ月前までの申込が推奨されています。
金融機関の教育ローンも審査状況により融資までにかかる時間が異なるため、いずれにしても時間に余裕を持って申込をしましょう。
公的支援制度を利用する
教育資金が不足する家庭や学生を支えるための、公的支援制度も存在します。
奨学金制度や教育ローンよりも詳細な規定がある場合が多く、対象者となる人は限られますが、利用できる制度があるなら活用してみましょう。
公的支援制度は金融機関から融資を受けるよりハードルが高い傾向にあるため、利用が難しいと感じた場合は、金融機関からお金を借りる選択肢も持っておきましょう。
| 主な公的支援制度 | 内容 |
|---|---|
| 生活福祉資金 教育支援金 | 市町村民税非課税程度の、資金の融通を他から受けることが困難な世帯に貸与する |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない世帯に貸与する |
カードローンを利用する
一時的に学費を支払えない場合は、カードローンの利用も有効です。
- カードローン
-
個人向け融資サービスの一種で、専用のローンカード等を使用して金融機関やコンビニなどのATMで取引が可能です。代表例として消費者金融のカードローンや銀行のカードローンがあります。
カードローンは20歳以上で安定的な収入があれば、学生でも申込が可能な金融機関が多いため、パートやアルバイトでも毎月一定の収入を得ていれば借入できる可能性があります。カードローンによっては最短即日融資も可能であるため、学費の納入期限が迫っている場合にも対応できます。
ただし、総量規制という法律により、年収の3分の1を超える借入ができません。アルバイトなどで収入が少ない学生は、少額しか借りられない可能性もあるので注意してください。
- 総量規制
-
消費者金融やクレジットカード会社などを対象に設けられている法制度の1つです。返済能力を超えた過剰な貸付から消費者を守るために、「年収の3分の1を超える貸付の原則禁止」を定めています。
SMBCモビットのカードローンはアルバイトでも申込できる
SMBCモビットのカードローンは、満20歳以上74歳で安定した収入がある方が対象と定められています。したがって、20歳以上の学生で、アルバイトなどで毎月一定の収入を得ていれば申込可能です。
即日融資にも対応しており、来店不要でスマートフォンからお手続きできるので、学費の補填や、一時的な生活費に充てるといった活用方法をご検討ください。
※お客様の状況により希望に添えない場合があります。
※お申込の時間帯や審査の状況により、融資完了までにお時間がかかる場合があります。
親族や親戚から支援を受ける
親族や親戚から支援を受けるのも選択肢の1つです。贈与となると税金がかかることが心配になる方もいるかもしれませんが、必要なときに必要な金額を贈与する「都度贈与」であれば非課税扱いになります。
都度贈与で非課税となるのは原則として年間110万円までです。しかし、教育費用の贈与であれば、110万円以上の支援であっても非課税となります。
贈与の事実と使い道が明確になるよう、資金は現金ではなく金融機関に振込してもらい、学費として支払った際の領収書も保存しておきましょう。
贈与についてはその他細かいルールもあるため、心配の方は専門家に相談したうえで判断しましょう。
一時的な休学を検討する
休学中は授業料の納付を止められるため、一時的に休学してアルバイトなどで費用を用意するのも1つの方法です。
ただし、授業料がかからなくても、1万円〜20万円程度の在籍料が必要なケースが一般的です。また、大学や学部によっては在籍料以外にも互助会費や学会費が徴収される場合があります。
実際に休学した場合の必要金額を大学の担当者に確認し、在籍料を払ってでも休学することにメリットがあるのか、よく検討してから決断しましょう。
将来の学費の支払いに備える方法
将来的に大学への進学を考えている子どもがいる世帯は、今のうちに大学の学費を貯めておくと有効です。
短期間で多額の資金を用意するのは難しくても、大学進学まで一定の時間をかければ無理なく準備できる可能性があります。あらかじめ複数の方法を確認し、早い段階から学費の支払いに備えましょう。
将来の学費の支払いに備える方法
- 児童手当を貯蓄しておく
- 学資保険を利用する
- NISA制度を活用する
児童手当を貯蓄しておく
児童手当とは、児童の健全な育成と家庭の生活の安定を目的に、年齢に応じて10,000円〜15,000円の手当が支給される制度です。現行の制度では、高校修了前の児童を養育する家庭が支給対象となります。
たとえば3月生まれの子の場合、支給額の合計は234万円になります。児童手当の支給合計額は以下の通りです。
| 0歳〜3歳未満 (3歳の誕生月まで) | 15,000円×12カ月×3年=540,000円 |
| 3歳〜小学校修了まで | 10,000円×12カ月×9年=1,080,000円 |
| 中学校入学〜高校修了まで | 10,000円×12カ月×6年=720,000円 |
| 合計 | 2,340,000円 |
この金額をすべて学費の支払いに充てられれば、大きな助けになるはずです。
生活費とは別の銀行口座に貯蓄しておけば、誤って生活費として使うことはないでしょう。児童手当は年3回定期的に振込されるので、積立預金などで計画的に貯蓄するのも有効な方法です。
ただし、児童手当には子どもの人数に応じて所得制限が設定されているため、すべての家庭が同じ金額を受給できるわけではありません。
児童手当の所得制限については、こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」に詳細が載っているので、気になる方は確認をしてください。
学資保険を利用する
学資保険は、子どもの将来の学費の支払いに備えるための保険商品です。毎月一定の保険料を支払うことで計画的に学費を貯められ、満期時には支払った保険料を上回る保険金を受け取れます。
また、保険期間中に契約者(保護者)が死亡した際には以降の保険料の支払いは必要なく、満期時には保険料を全額支払った場合と同額の保険金が受け取ることになります。
ただし、中途解約をした場合、解約返戻金が支払った保険料の金額を下回る場合があることには注意してください。
- 解約返戻金
-
生命保険や貯蓄型保険などの保険契約を途中で解約した時に受け取れる返金額を指します。契約年数や契約内容、支払済みの保険料などによって受け取る金額は異なります。
NISA制度を活用する
老後の資金の準備に活用されることの多いNISA制度を、学費の準備に活用することもできます。
NISA制度とは、2014年1月に開始された少額投資非課税制度です。2018年につみたてNISAが開始されたのち、2024年1月に新制度が開始されました。
つみたて投資枠と成長投資枠の2つの投資枠が併用でき、合計で1,800万円が非課税で運用できます。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 非課税保有期間 | 無制限 | 無制限 |
| 制度(口座開設期間) | 恒久化 | 恒久化 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円 | 1,200万円 (つみたて投資枠の1,800万円の中に含まれる) |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 (金融庁の基準を満たした投資信託に限定) | ・上場株式 ・投資信託 等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
非課税保有期間が無制限かつ非課税保有限度額の再利用が可能であるため、必要なときに運用商品を解約して都度現金化し、また経済的に余裕が生まれたタイミングで運用を再開できるのがメリットです。
NISA制度は長期的な資産形成に向いており、子どもの将来の学費を計画的に積み立てるのに適しています。
ただし、投資信託などの運用商品にしか利用できないため、元本の保証はありません。学費が必要になるタイミングによっては、相場が下落して資産が目減りしている可能性もあります。
投資にはリスクが伴うため、リスク許容度や投資期間を考慮し、慎重に運用することが重要です。
よくある質問
Q.学生でもお金を借りられますか?
A.アルバイトなどで収入があれば借入できる可能性があります。
大学生でも、アルバイトなどで本人に安定した収入があれば借入は可能です。ただし、金融機関によって、18歳以上もしくは20歳以上といった年齢制限があるので注意してください。
20歳未満の場合には、「20歳以上で安定した収入があること」といった条件を設けている金融機関に申込をしようとしても、審査に通過できません。とくに20歳未満の学生は、事前に借入を希望する金融機関の申込条件を確認してください。
Q.保護者に教育ローンを組んでもらうことは可能ですか?
A.保護者名義で教育ローンを組むことも可能です。
教育ローンは基本的に保護者が契約者になるものです。そのため、保護者を頼る場合は、銀行などの教育ローンをご検討ください。なお、学生本人が自分で組める教育ローンもありますが、収入が少ないなどの理由で融資を断られてしまう可能性があります。
そういった場合は、奨学金を利用して自分名義でお金を借りるなどの対応を検討してください。
Q.除籍・退学となった場合、あらためて入学できますか?
A.再入学期限が設けられている場合もありますが、基本的には可能です。
基本的に、除籍処分や自主退学となった場合であっても、あらためて入学できます。ただし、大学によって入学試験や入学金の支払いなどの条件が設定されている場合があります。また、退学後の再入学期限を設けている大学もあり、一般的には退学後2〜4年以内でなければ再入学は難しい状況です。
再入学のルールは大学によって異なるため、希望する場合は事前に大学に確認しておきましょう。その上で、休学も視野に入れて検討してください。
学費を早く用意したい方は状況に応じてSMBCモビットをご検討ください
大学生が学費を支払えなかった場合、除籍処分や自主退学となる可能性があります。今後の就職活動等にも影響を与えかねないため、奨学金制度や教育ローン、カードローンの利用を検討しましょう。
中でもカードローンは、学生本人にアルバイトなどで安定した収入があれば借入できる可能性があります。
カードローンの利用を考えている方は、ぜひSMBCモビットをご検討ください。

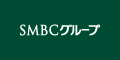



監修者コメント
荒井 美亜
貸金業務取扱主任者 みんなのモビット担当
大学を除籍されてしまうと大卒の扱いにはならないため、就職する際の選択肢が狭まってしまう可能性があります。大卒になるためには必ず卒業する必要がでてくるので、学費にどれくらいの金額がかかるのか、事前に計算しておきましょう。